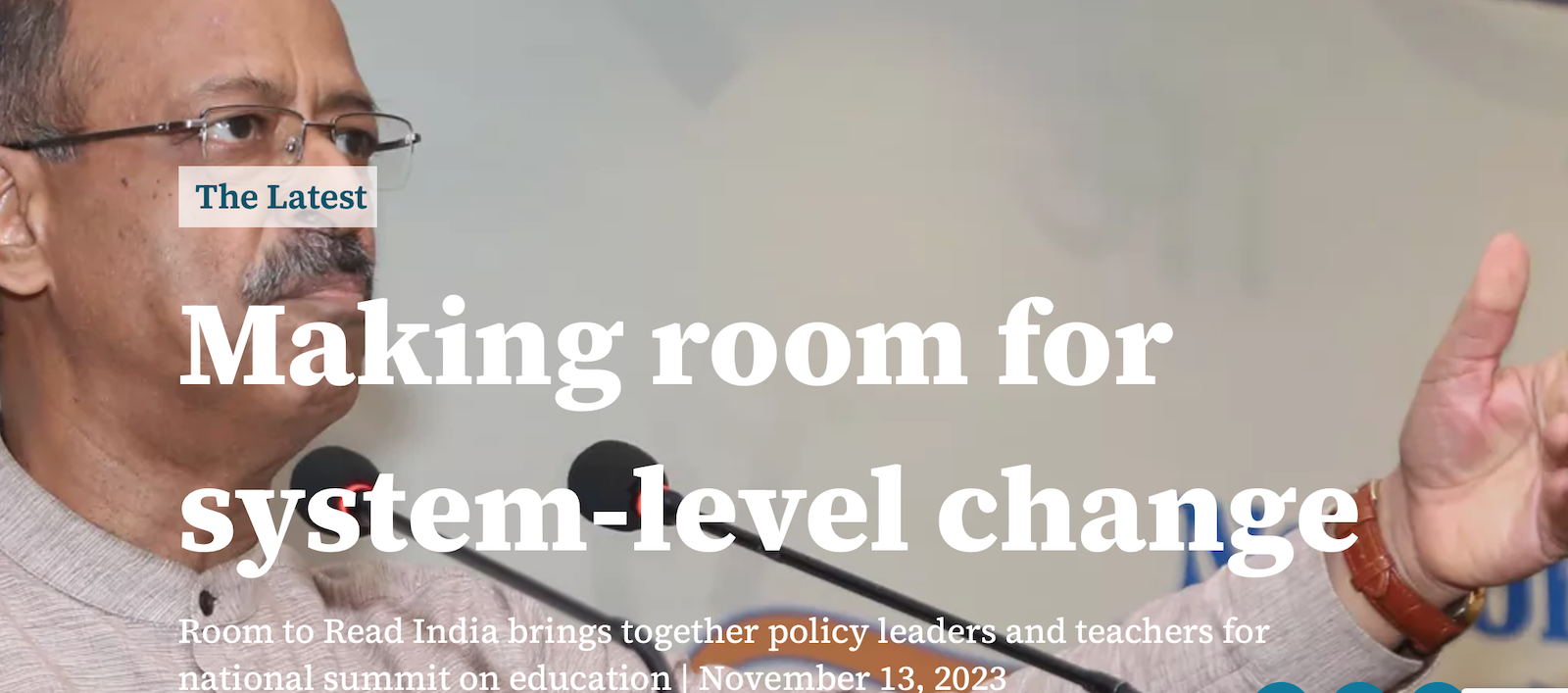ボランティアの皆様、ルーム・トゥ・リード・ジャパンの理事・友人、職員と共に 📍東京マラソン2024(2/29-3/3)ボランティアを募集中!(募集締切 2/21)🎉 ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー 2024年3月3日(日)の東京マラソン に際し、ボランティア/インターンを募集しています。
東京マラソンは世界6大会の一つであり、プロからアマチュア、海外ランナーまで38,000名余りが走行する国際大会です。当日は25か国から150名(9割外国人)がルーム・トゥ・リードのチャリティランナー として東京を駆け抜けます。
ランナーの皆さんがどんな思いでフルマラソンを走るのか、お読みください。
「ディスレクシア(難読症)を抱えて育ちました。ルーム・トゥ・リードが展開するような絵本にアクセスできなければ、成功したキャリアを築くのに苦労したことでしょう。」
「金銭による寄付など一化性ものでなく、自らの能力や知識を高めて、子どもが力を身につけるサポートを行いたいと思い申し込みました。」
一緒にチャリティランナーを応援し、ダイナミックな大会を体感しませんか?ご協力いただく時間は数時間でも構いません。「英語は苦手だけどチャレンジしたい!」という方も大歓迎です。チャリティTシャツ と、現地語のデジタル絵本 (翻訳付き)をプレゼント!ぜひ、ご参加ください。
【1】EXPOブース運営2月13日更新:こちらの募集は締めきりました。3月3日の沿道応援のご協力を引き続きお待ちしております!
<ボランティア時間枠> ①日中(10:00~14:00) ②夕方(14:00~18:00) ③夜(18:00 以降) ※4 時間以下の参加希望についてもぜひご相談ください!
●場所:東京ビッグサイト(締め切りました)
【2】マラソン当日チャリティブース運営2月13日更新:こちらの募集は締めきりました。沿道応援のご協力を引き続きお待ちしております! <ボランティア時間枠> ①日中(10:00~14:00) ②夕方(14:00~18:00)
●場所:東京商工会議所(締め切りました)
【3】沿道応援 <ボランティア時間枠> ①日中(10:00~14:00) ②夕方(14:00~18:00)
●場所:両国駅、田町駅など、各拠点
【その他】
■ご応募 募集締切:2月25日(日) japan@roomtoread.org へお問合せください
📍ボランティアの声(東京マラソン2023年大会をサポート) ● チャリティーブースの運営では、寄付者とのコミュニケーション はもちろん、他のチャリティ参加団体の支援内容についても学ぶことができます。サステナビリティ感度を高めたい方、時代の最先端でどのような社会課題があるのか勉強したい方 にもうってつけです。また当日の沿道応援では、東京マラソンの熱気を直に感じることができます。是非一緒に寄付者に声援を届けましょう!
● 昨年度、当日チャリティーブース運営スタッフとして参加させていただきました。普段の生活では出会うことのできない素敵な方々と会話することで、自分の人生においてとても貴重な体験 となりました。参加を迷われているそこのあなた!参加して絶対に後悔しないと思います! (塩瀬様) ★実際のチャリティランナーの声はもちろん、ボランティアの活躍もご覧ください! http://roomtoreadjapan.org/2023/08/tokyo2024_150runners.html http://roomtoreadjapan.org/2022/10/tokyolegacy2022.html http://roomtoreadjapan.org/2023/02/2weekstorun.html






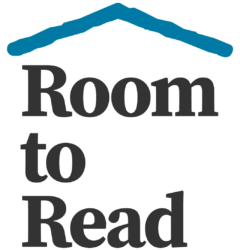





 ●日時:
●日時:
 ●日時:3/3(日) 10:00-16:00頃
●日時:3/3(日) 10:00-16:00頃